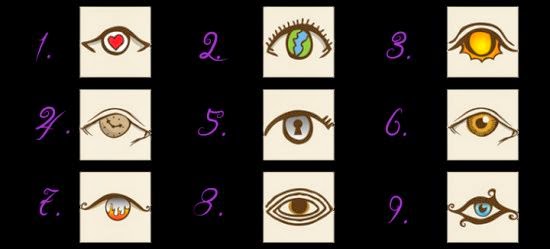|
| 十代目金原亭馬生 噺と酒と江戸の粋 |
幼い頃、私は自分の誕生日を二七日だと思っていた。たぶん、誰かにそう教えられたのだろう。二八日だと記憶を訂正されたのは、小学校に上がる頃だった。この偽の記憶については、親父が主犯であろうとにらんでいる。親父は私が大学を卒業するときも、何かの書類に「二七日」と書いていたので、私が訂正した憶えがある。
別に深夜に産まれたわけでもないのだが、ちょっと居心地の悪い話だ。
とはいえ、落語家の十代目金原亭馬生に比べれば対したことはない。彼の父親は今や伝説と化した古今亭志ん生
長じて馬生は志ん生に質してみた。
「おとっつぁん、ほんとのとこ、おいらはいつの生まれなんだい?」
志ん生応えて曰く。
「ばかやろう、生まれたんだからそれでいいじゃねえか」